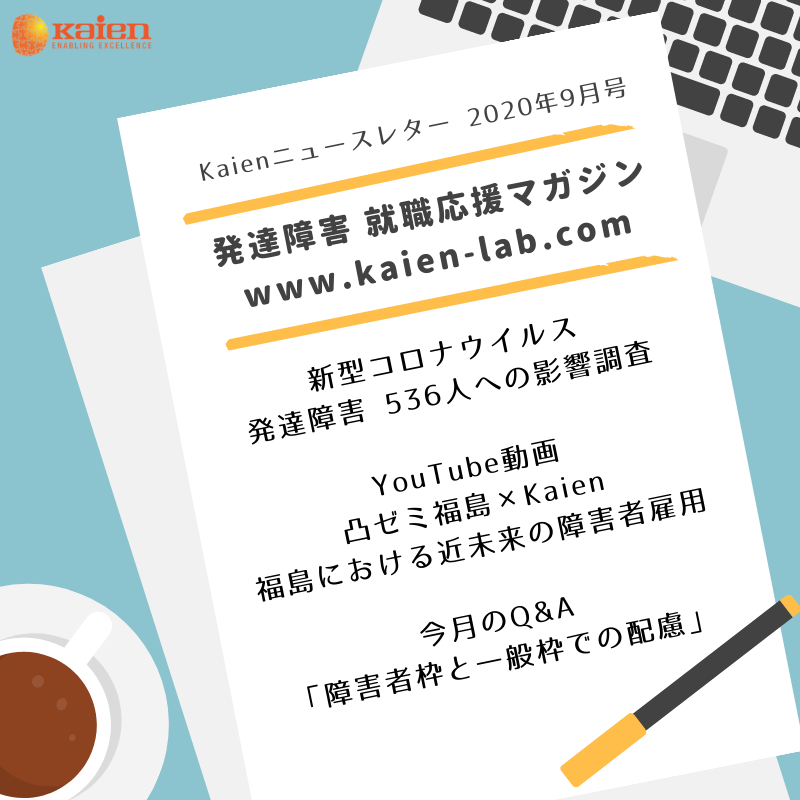
1. 新型コロナウイルス 発達障害* 536人への影響調査
在職者300人のアンケート、そして障害福祉サービス(就労移行・生活訓練)などに通う236人の利用者に協力してもらった、新型コロナウイルスの影響アンケートです。
第二波を通じて、雇用が不安定になっている人がジワリと増えている印象です。また障害者雇用への影響も出始めて、就職活動への焦りも数字に反映されていると感じます。
新型コロナウイルス 発達障害の在職者(300人)への影響
Kaien独自調査 2020年8月24~31日
新型コロナウイルス 発達障害の障害福祉利用者(236人)への影響
Kaien独自調査 2020年8月24~31日
2. YouTubeチャンネルからピックアップ
KaienのYouTubeチャンネルから厳選動画をピックアップ。ウェブサイトでご確認いただけます。
厳選動画をご紹介
凸ゼミ福島×Kaien 福島における近未来の障害者雇用(2020年8月27日開催分)
「目指せ!発達障害の支援者」~Kaienの支援者育成メソッド、全部お伝えします~(2020年8月28日開催分)
3. イベント情報
無料配信のイベントを複数開催。ウェブ開催「お勧め!今月の無料イベント」でご確認いただけます。
-
9/18(金)19:00 創業記念セミナー『Kaienオンライン支援 半年の振り返り ~福祉事業の未来像を考える~』
ウェブ開催!無料イベント
そのほか下記の外部イベントに登壇しました。
- 8/30 星槎大学 「キャリアデザイン2」
講演・研修依頼
4. 今月のQ&A
お寄せいただいた質問に当社代表取締役の鈴木慶太がお答えします。
障害者枠での配慮と一般枠での配慮
Q1. 障害者枠で就労する場合、行われる配慮はどの程度、就労者の要望を汲まれたものになるのか?
A. 障害者雇用だけではなく、一般雇用でも法律に基づいた「合理的配慮」は受けられます。ですので、配慮を受けるには障害者雇用でなくてはいけないわけではありません。しかし障害者雇用は、「合理的配慮」とは別の文脈で既に日本に制定されていた「障害者雇用促進法」で定義されて歴史が古くあります。ですので、障害者雇用では「合理的配慮」のレベルをより進めた配慮を求められるでしょう。つまり何が合理的なのかは障害者雇用のほうが働く人に寄り添ったものになりやすいということです。
ただし企業によってまた職場によって、どこまでを受け入れるか、あるいはどんな種類の配慮を受け入れるかは、違いがあります。Kaienでは、障害特性(配慮を受ける根拠)、自分でしている工夫、を伝えた上で、配慮の要望をすること、そしてその配慮を受けるとどのように自分が戦力化されるかの順で考えるようにお伝えしています。
そして大事なのは、配慮の種類や程度は、同じ人が働く場面でも仕事内容や周囲の環境によって、徐々に変化するものだと思います。半年に一度など定期的に上司や人事と面談を持ち、今どんな配慮が求められているかを伝えましょう。こういった定期的なやりとりも障害者雇用だとスムーズに行われやすいでしょう。
発達障害 仕事がうまくいく 合理的配慮の求め方
発達障害 仕事がうまくいく 合理的配慮の求め方
パートナー事業所とKaien直営店の違い
Q2. パートナー企業ですと、直営の事業所とどれくらい支援内容に差があるのでしょうか。
A. Kaienは直営事業所とパートナー事業所があります。首都圏と大阪(天神橋筋六丁目)の9事業所は当社の直営事業所です。一方でパートナー事業所は現在全国に11あります(まもなく北海道に最初のパートナー事業所がオープンします)。直営事業所はスタッフも当社社員で、パートナー事業所はそれぞれの法人の社員・職員が運営しています。またパートナー事業所は当社のプログラムだけではなく、それぞれの事業所のオリジナルの教材やプログラムも行われています。このため、支援内容はパートナー事業所の間でも変わります。ぜひ事業所に直接お確かめください。
Kaien・TEENSのパートナー一覧
https://corp.kaien-lab.com/partners/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%a3%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e4%b8%80%e8%a6%a7
本人が前向きになれないとき
Q3. 発達障害(ASD)として、大学の支援室にも相談していましたが、紹介されるイベントなどにもなかなか参加する意欲が持てないまま、修学に向けた意識が低下してしまい、退学を検討しています。このように本人が前向きに参加しようという気持ちを持てない場合に、修学に向けた意識形成や、対人関係を良好に行えるようにしていくためにはどのような支援が考えられますでしょうか?
A. 当社につながる方はその気持ちが少しでも持てた方がいらっしゃいます。このためその前の段階の支援については当社の専門外ともいえるかもしれません。一方で当社のウェブサイトを見たり、説明会に参加したりぐらいの前向き力があるならば、読んだり聞いたりするなかで次への希望を感じていただける可能性もあります。当社のサービスでは生活訓練が一番近い内容になりそうです。現在市ヶ谷だけですが、今後、立川、さいたまなど首都圏や関西にも展開予定です。周囲の方が焦ったり疲れない様にしたりするのが一番重要です。先回りして情報を集めながら本人が少し前向きになったときに次への方向性を示すカードをいくつか用意されると良いと思います。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)サービスについて
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189